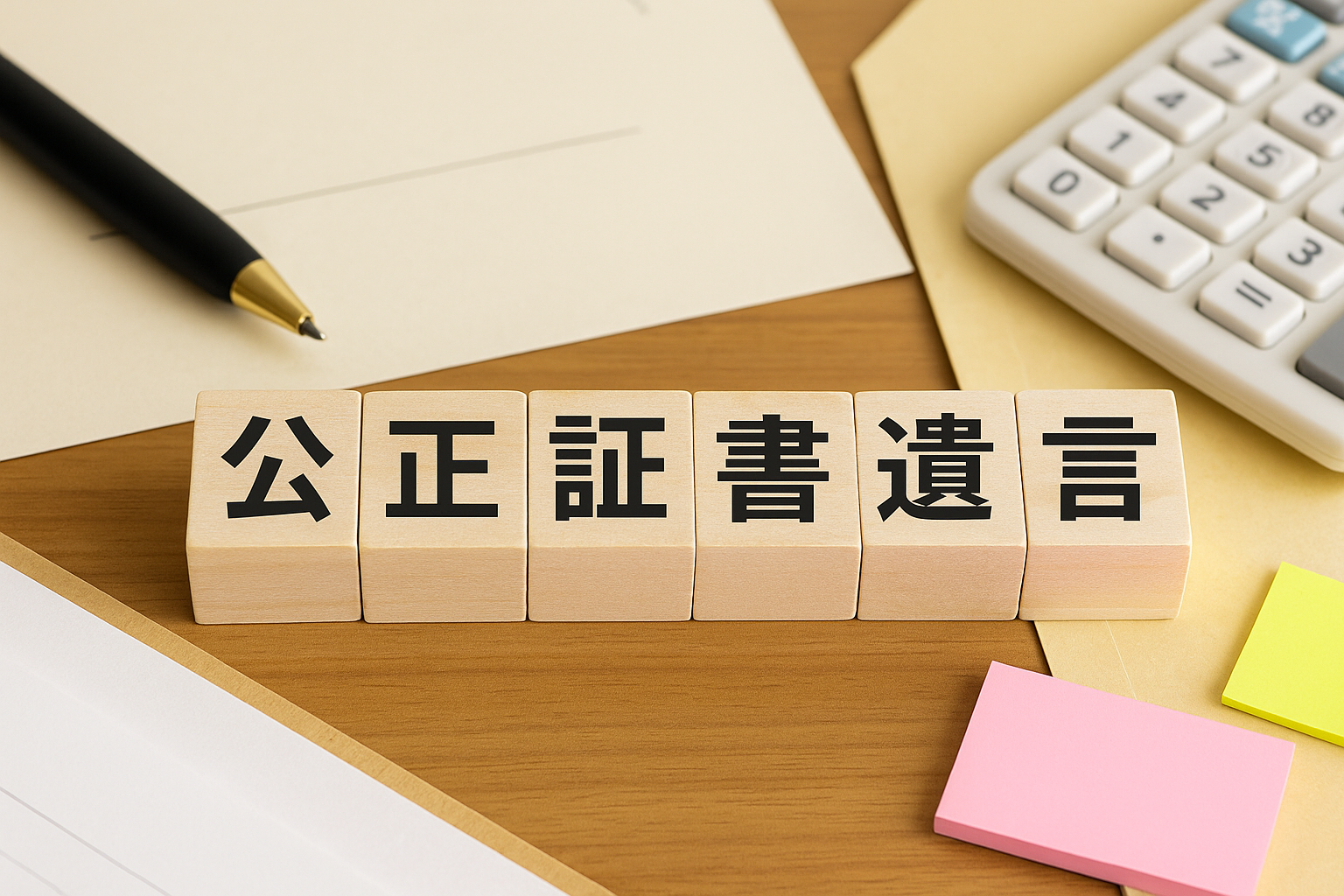この記事を要約すると
- 公正証書遺言の作成には、公証人手数料や証人謝礼、必要書類の取得費用など、複数の費用項目が発生します。
- 財産の金額や分け方、証人の手配、出張の有無、司法書士への依頼などによって費用は大きく変動します。
- 自分で作成すれば費用は抑えられますが、手間やミスのリスクもあるため、司法書士に依頼することで安心・確実に進められます。
1. 公正証書遺言の費用と基本の内訳
公正証書遺言を作成するには、財産の金額や作成方法に応じてさまざまな費用がかかります。なかでも必ず発生するのが、公証人に支払う手数料や必要書類の取得費用です。
また、証人を依頼したり、公証人に出張してもらう場合には追加費用が発生します。ここでは、その基本的な費用項目について詳しく解説します。
なお、以下の記事では、公正証書遺言の作成手順や作成する際の注意点を詳しく解説しています。ぜひ、あわせてチェックしてみてください。
1-1. 公正証書の作成手数料(公証人手数料)
公正証書遺言の作成には、公証人役場に支払う「公証人手数料」が必要です。
この手数料は、遺言書に記載する財産の価額に応じて決まりますが、財産の相続または遺贈を受ける人ごとに手数料額を求め、これらの手数料を合算して全体の手数料を算出する点に注意してください。
以下は、基本的な財産価額ごとの手数料の目安です。
| 財産価額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円超~200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円超~500万円以下 | 11,000円 |
| 500万円超~1,000万円以下 | 17,000円 |
| 1,000万円超~3,000万円以下 | 23,000円 |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 29,000円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超える財産については、以下の加算方式が適用されます。
| 財産価額の範囲 | 手数料加算方式 |
|---|---|
| 1億円超~3億円以下 | 43,000円 + 超過額5,000万円ごとに13,000円加算 |
| 3億円超~10億円以下 | 95,000円 + 超過額5,000万円ごとに11,000円加算 |
| 10億円超 | 249,000円 + 超過額5,000万円ごとに8,000円加算 |
財産の総額が1億円以下である場合は「遺言加算」として、11,000円が別途加算されます。
さらに、遺言公正証書は、通常、原本、正本および謄本を各1部作成するため、その手数料が必要になります。
| 区分 | 1枚あたりの単価 |
|---|---|
| 原本(※) | 250円 |
| 正本 | 250円 |
| 謄本 | 250円 |
※4枚(法務省令で定める横書きの公正証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算されます。
たとえば、原本が縦書き5枚、正本・謄本が各5枚のケースでは次のような費用になります。
- 原本手数料(基準4枚を超えた1枚分)=250円
- 正本手数料(5枚×250円)=1,250円
- 謄本手数料(5枚×250円)=1,250円
- 合計=2,750円
1-2. 必要書類の取得費用(戸籍・登記事項証明書など)
公正証書遺言の作成には、手数料のほかにも以下のような必要書類の取得費用が発生します。
- 戸籍謄本:1通450円
- 不動産登記事項証明書(謄抄本):1通500~600円
- 住民票:1通200~300円(自治体による)
- 印鑑登録証明書:1通200~300円(自治体による)
- 固定資産評価証明書:1通200~400円(自治体による)
書類の取得費用や郵送代等の実費として、5,000円から1万円を考えておくとよいでしょう。
1-3. 証人の謝礼や出張時の追加費用
公正証書遺言の作成には、原則として証人2名の立ち会いが必要です。証人を自前で用意する場合は費用はかかりませんが、公証人役場や専門家に依頼する場合は、1人あたり5,000円~1万5,000円程度の謝礼が必要です。
また、遺言者が高齢や病気などの理由で公証人役場へ出向けない場合は、公証人に自宅や病院などへ出張してもらうことができます。この場合、通常の手数料に加え、証書作成手数料額の50%の加算料金、日当(1~2万円)、交通費などが必要になります。
状況によっては、出張費用だけで2万円以上かかることもあるため注意が必要です。
2. 【ケース別】費用のシミュレーション
公正証書遺言の作成にかかる費用は、財産の分け方や相続人の人数によって変動します。実際にどの程度の費用がかかるのかを具体的に把握するには、ケースごとのシミュレーションが有効です。
ここでは、典型的な2つのパターンを想定し、それぞれの費用内訳と総額の目安をご紹介します。
2-1. 配偶者1人に全財産3,000万円を相続させるケース
配偶者1人に対して全財産3,000万円を遺贈する内容の公正証書遺言を作成する場合、以下の費用が発生します。
- 公証人手数料:2万3,000円
- 遺言加算:1万1,000円
- 正本・謄本手数料:2,000円程度(各4枚として想定)
- 必要書類収集費用:5000円程度
合計で、およそ4万円程度が基本費用の目安となります。また、ここに証人依頼や出張が必要な場合は、別途費用が加算されます。
2-2. 配偶者に2,000万円、子ども2人に1,000万円ずつ相続させるケース
相続人3名に異なる割合で分配するケースでは、さらに手数料が増えます。
- 配偶者(2,000万円):2万3,000円
- 子ども1(1,000万円):1万7,000円
- 子ども2(1,000万円):1万7,000円
- 遺言加算:1万1,000円
- 正本・謄本手数料:2,000円程度
- 必要書類収集費用:5,000円程度
合計で、およそ7万5,000円前後になります。受け取る人が多いほど、公証人手数料は比例して高くなるため、事前の試算が重要です。
3. 公正証書遺言の作成費用を左右する4つのポイント
公正証書遺言の作成費用は一定ではなく、状況や条件によって大きく変動します。具体的には、財産の金額や受け取る人の人数、証人の手配、出張の有無、そして専門家に依頼するかどうかといった要素が影響を与えることになります。
ここでは、費用に差が出る4つの代表的なポイントを詳しくみていきましょう。
3-1. 財産の金額が高額かどうか
公正証書遺言の手数料は、遺言で指定される財産の「各相続人ごとの金額」に応じて決まります。そして、財産が高額であるほど、その相続人に対する手数料も高くなります。
たとえば、1,000万円を相続させる場合の手数料は23,000円、4,000万円なら29,000円となり、分け方によって費用全体が変動します。
3-2. 公証人の出張が必要かどうか
遺言者が高齢や病気で公証役場に出向けない場合、公証人に出張を依頼することができますが、その分費用が増加します。
通常の手数料の他に書類作成手数料額の50%の加算料金が発生し、日当(目安として1〜2万円程度)や交通費も必要になります。出張は便利な反面、全体の費用を押し上げる要因となるため注意が必要です。
3-3. 証人を自前で用意できるかどうか
公正証書遺言の作成には2名の証人が必要です。自分で証人を用意できれば費用はかかりませんが、公証役場に依頼する場合は1人あたり1万円前後の謝礼が必要になります。
2名分の依頼となると、2万円前後の費用がかかることもあります。証人を用意できるかどうかで費用に差が出ます。
3-4. 司法書士など専門家への依頼の有無
公正証書遺言の作成にかかる費用は、自分で手続きを行うか、専門家に依頼するかによって大きく異なります。
公正証書遺言は司法書士等専門家に依頼せずに作成することは可能ですが、内容に不備があると無効になるリスクがあります。そのため、司法書士など専門家にサポートを依頼する方も多く、報酬の目安は10〜20万円程度です。
専門家に依頼する場合、専門家への報酬の支払いが増えることになりますが、書類準備から公証役場との連携まで任せられ、安心して手続きを進められるメリットがあります。自分で作成する場合と司法書士等専門家に依頼する場合の出費の差額は、概ね専門家への報酬額分(10~20万円)となります。
4. 公正証書遺言を司法書士に依頼するメリット
公正証書遺言は、司法書士等専門家に依頼しなくても作成できますが、法律的に有効かつスムーズに手続きを進めるためには、専門家のサポートを受けることが有用です。
煩雑な手続きをすべて任せられるため、初めて遺言書を作成する方や、不動産や相続人が絡む複雑なケースでは、専門家のサポートを受けることでスムーズかつ確実な遺言作成が可能になります。
ここでは、司法書士に依頼することで得られる具体的なメリットを紹介します。
4-1. 書類の準備や打ち合わせもまるごと任せられる
公正証書遺言を作成するには、戸籍や登記事項証明書などの必要書類をそろえる必要があります。また、公証人との打ち合わせや日程調整の手間も発生します。
司法書士に依頼すれば、こうした事務手続きを一括で任せることができるため、ご自身の負担を大きく減らせます。
4-2. 相続登記など、死後の手続きもスムーズに連携できる
司法書士は、不動産の名義変更(相続登記)にも対応しているため、遺言内容に基づいた死後の手続きもワンストップで進められます。
公正証書遺言の内容と相続登記が矛盾しないよう、事前の設計段階から専門的にアドバイスを受けられるのも大きなメリットです。
4-3. 実務経験が豊富な司法書士なら相続トラブルも予防できる
相続には家族間の感情や利害が絡むことも多く、ちょっとした記載ミスや曖昧な表現が将来的なトラブルの火種になることもあります。
実務経験が豊富な司法書士であれば、そうしたリスクを見越した文案作成やアドバイスが可能です。結果として、遺された家族が争わずにすむ、安心できる遺言が実現します。
5. よくある質問・Q&A
ここでは、公正証書遺言の費用や司法書士への依頼について、よく寄せられる疑問にお答えします。事前に気になる点を確認しておくことで、安心して準備を進めることができます。
| Q1. 公正証書遺言の作成を司法書士に依頼すると、いくらかかる? |
| A1. 司法書士への依頼費用は、事務所ごとに異なりますが、一般的には5〜15万円程度が相場です。依頼内容には書類収集や文案作成、公証人との打ち合わせなどのサポート費用等が考えられますが、詳細は各事務所に確認しましょう。 |
| Q2. 自分で作成する場合、どの程度費用を抑えられる? |
| A2. 公正証書遺言を自分で作成すれば、司法書士への報酬がかからない分、支出総額は5〜15万円程度抑えられるでしょう。専門家へ依頼するメリットとあわせて、検討してみましょう。 |
| Q3. 公正証書遺言の作成には、手数料のほかにどんな費用がかかる? |
| A3. 公正証書遺言の作成には、作成手数料のほかにも以下のような費用が発生することがあります。 事前に全体の費用感を把握し、必要に応じて見積もりを取得しておくことが、安心して遺言作成を進めるうえで重要です。 |
| 費目 | 内容・条件 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 必要書類の取得費用 | 戸籍謄本・住民票・ 登記事項証明書・評価証明書など | 約200~750円/通 |
| 証人の謝礼 | 公証人役場や専門家に依頼した場合 | 5,000~1万5,000円/人 |
| 公証人の出張費(任意) | 自宅・病院などへ出張が必要な場合 | 通常手数料の50%加算+ 日当1~2万円+交通費 |
6. 費用も安心も見据えて、公正証書遺言は司法書士への依頼を検討しよう
公正証書遺言の作成には、公証人の手数料や証人謝礼、謄本の発行費用など、一定の費用がかかります。また、遺言内容の整理や必要書類の取得、公証役場とのやり取りなども含めると、想像以上に手間がかかるものです。
さらに、文案のミスや記載漏れがあると、せっかく作成した遺言が無効となるおそれもあります。こうしたリスクを回避するためには、専門知識をもつ司法書士への依頼を検討するのがおすすめです。
相続手続きの専門集団「nocos(NCPグループ)」では、公正証書遺言の作成支援も含めて、司法書士や行政書士などの専門家が連携して対応しています。複雑なケースにも実績があり、初回相談は無料。オンライン相談にも対応していますので、お気軽にお問い合わせください。