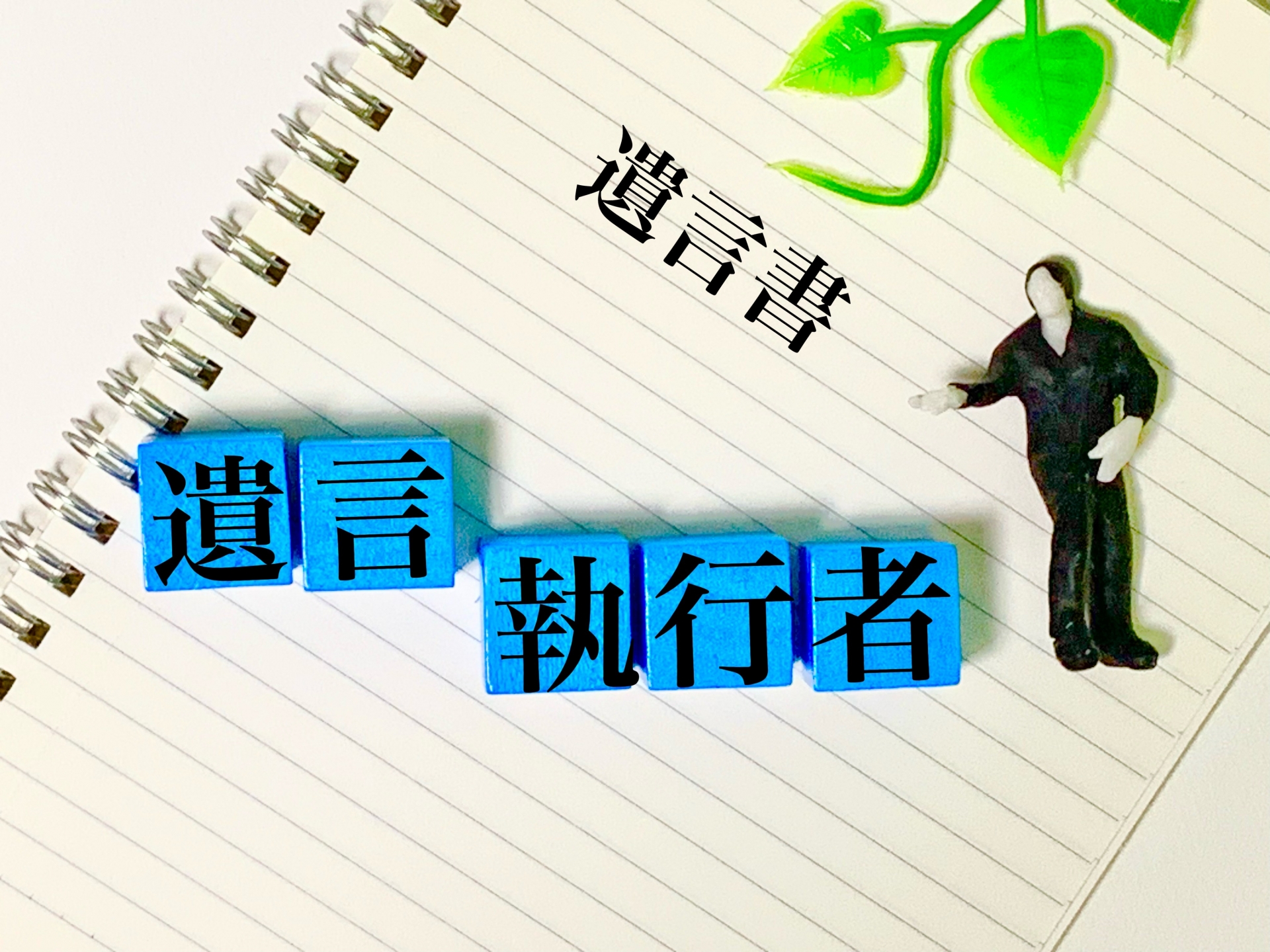この記事を要約すると
- 相続人を遺言執行者にすることは法律上可能ですが、不信感や業務負担などのリスクがともなうため慎重な判断が必要です。
- 専門家に遺言執行を依頼することで、中立的かつ確実に手続きを進められ、相続人の心理的・時間的負担も軽減できます。
- 費用はかかるものの、弁護士や司法書士などの専門家に相談することで、相続全体のトラブルを未然に防ぐことができます。
1. 遺言執行者と相続人は同一人物でも法的に問題ない?
遺言執行者と相続人が同一人物であっても、法律上はまったく問題ありません。
民法上、遺言執行者には未成年者や破産者でない限り誰でも就任できるとされており、相続人であっても要件を満たしていれば指定可能です。
また、遺言執行者は1人に限らず、複数人を指定することもできます。
たとえば、不動産については長男、預貯金については二男など取得する遺産ごとに役割を分担して定めることも可能です。ただし、遺言執行者には、相続財産の名義変更や遺贈の手続きなど、法律的かつ実務的な作業がともなうため、選任にあたっては慎重な判断が求められます。
特に相続人のなかから遺言執行者を選ぶ場合は、他の相続人からの不信感や疑念を招く可能性があるため、遺言者の意思を明確に示すだけでなく、選任理由もあわせて記載しておくとトラブル防止に役立ちます。
2. そもそも遺言執行者とは?
遺言執行者は、遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う人です。まずは、その役割や選ばれ方について整理しておきましょう。
2-1. 遺言執行者の主な役割
遺言執行者の主な役割は、遺言書に記された内容を実現することです。
たとえば、特定の財産を誰に相続・遺贈するかといった内容に基づき、不動産の名義変更や預貯金の解約・分配などの実務手続きを進めます。
特に第三者に遺贈する場合など、相続人以外の人物が関与するケースでは、利害関係の調整や法的手続きが複雑になるため、遺言執行者の存在が重要になります。
なお、遺言に指定された内容のみに権限があるため、それ以外の事項には関与できません。
2-2. 遺言執行者の選任方法
遺言執行者は、原則として遺言書の中で遺言者が自ら指定します。たとえば、「長男〇〇を遺言執行者に指定する」と記載しておくことで、法的に有効な選任となります。
一方、遺言書に指定がない場合や指定された人物が辞退した場合は、家庭裁判所に申し立てて選任してもらうことも可能です。遺言執行者には特別な資格は必要ありませんが、未成年者や破産者は就任できないと民法で定められています。
選任後は、遺言執行者が相続人に対して就任の通知を行い、正式に手続きを開始します。就任には必ずしも同意書などの手続きは必要ありませんが、遺言執行の円滑化のために事前の了承を得ておくと安心です。
3. 相続人と遺言執行者を同一人物にすることで生じやすいリスク
相続人を遺言執行者に指定することは法的に問題ありませんが、実務上はいくつかのリスクが生じる可能性があります。ここでは代表的なリスクを具体的に解説します。
3-1. 他の相続人との間で不信感が募ったりトラブルが起きやすい
相続人の一人が遺言執行者になると、「自分に有利に進めているのではないか」といった疑念を他の相続人に抱かれやすくなります。たとえ公正に手続きを行っていても、不信感がきっかけで相続トラブルに発展するケースも少なくありません。
とくに、遺産の分配に関して利益相反の状況が生じる場合や、遺言内容が一部の相続人に不利な場合には、遺言執行者の言動がより強く疑念の対象になりがちです。遺産分割協議の妨げにもなり得るため、慎重な判断が大切です。
3-2. 知識不足によって手続きが滞ることがある
遺言執行者には、相続財産の調査や名義変更、遺贈手続きなど幅広い業務が求められます。法律や登記、税務に関する一定の知識が必要となるため、相続人がその役割を担う場合、内容を理解しきれずに手続きが停滞してしまうリスクがあります。
特に、不動産の相続登記や相続税の申告などは期限が定められており、適切な対応がされないと罰則対象になる可能性もあります。
3-3. 一人の相続人に業務が集中し負担が偏る
遺言執行者には、遺言の内容を具体的に実行するという大きな責任があります。そのため、遺言執行者に選ばれた相続人だけが、他の相続人よりも多くの作業や連絡、判断を求められる状況になりがちです。
相続手続きは複雑で長期化することもあるため、精神的・時間的な負担が大きく、日常生活や仕事に影響を与えるケースもみられます。特に複数の不動産や金融資産がある場合は、負担が顕著になるでしょう。
3-4. 途中で専門家に依頼すると余計な費用と時間がかかる
遺言執行者が自身の力だけでは業務を完了できず、途中から弁護士や司法書士に依頼する場合、当初から専門家に依頼するよりも時間や費用がかかることがあります。依頼時に情報の整理や再確認が必要になるため、スムーズに引き継ぎできないケースもあります。
また、途中での方針転換が他の相続人に不安を与える要因にもなりかねません。事前に専門家へ依頼するかどうかを検討し、最適な形で遺言執行体制を整えておくことが望ましいでしょう。
4. 専門家に遺言執行を依頼するメリット
相続人ではなく、弁護士や司法書士といった第三者の専門家に遺言執行を任せることで、さまざまなトラブルや負担を未然に防ぐことができます。ここでは、具体的なメリットを3つご紹介します。
4-1. 中立の立場から手続きを進められる
専門家は相続人の一人ではないため、当事者同士の利害関係にとらわれず、公平・中立な立場から手続きを進めることができます。これにより、相続人間で感情的な対立が生まれにくくなり、冷静かつ円滑に遺言を執行することが可能です。
また、第三者が関与することで、相続手続きの透明性が高まり、他の相続人も納得しやすいという効果も期待できます。
4-2. 専門知識によりスムーズかつ確実に進行する
遺言執行には、不動産登記、預貯金の解約、税務申告など、幅広く専門的な知識が求められます。専門家に依頼することで、複雑な手続きも法律や制度に則ってスムーズに進められ、ミスや遅延のリスクを大きく軽減できます。
特に相続税の申告や不動産の名義変更など、期限や要件のある手続きにおいては、知識と経験のある専門家の関与が安心材料となります。
4-3. 相続人の心理的・時間的負担を大きく軽減できる
相続人が自ら遺言執行を行う場合、日常生活の合間を縫って手続きを進める必要があり、相当な時間と労力を要します。専門家に依頼すれば、これらの実務を一括して任せることができ、相続人の負担を大きく減らすことができます。
また、トラブル対応や法的判断をともなう場面でも専門家が対応してくれるため、精神的な安心感も得られます。大切な家族を亡くした直後の不安定な時期には、特に心強い存在といえるでしょう。
5. 遺言執行者として依頼できる専門家と費用の目安
遺言執行者には、法的な知識と実務経験が求められるため、専門家に依頼するケースが多くなっています。ここでは、主に依頼できる専門家の種類と、その費用の目安について解説します。
以下は、遺言執行者として依頼できる代表的な専門家と、費用の相場です。
| 専門家の種類 | 特徴 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 弁護士 | 相続トラブルや訴訟リスクの ある場合に適している | 遺産総額の0.5〜2% (最低30万円程度) |
| 司法書士 | 不動産の相続登記を含む 手続きに適している | 遺産総額の0.5~2% (基本料金25~30万円) |
| 税理士 | 相続税申告まで依頼したい 場合に適している | 遺産総額の1~2% (基本料金20~30万円) |
なお、専門家への報酬は遺産の内容や相続人の数、手続きの複雑さによって大きく変わるため、事前に複数の事務所から見積もりを取ることをおすすめします。
6. よくある質問・Q&A
遺言執行者に関する疑問は多くの人が抱くものです。ここでは、特によくある質問とその答えをQ&A形式でまとめて紹介します。
| Q1. 遺言執行者と相続人は同じ人でもいい? |
| A1. 法律上は遺言執行者と相続人が同一人物であっても問題ありません。遺言執行者には未成年者や破産者でない限り、誰でも就任可能です。 ただし、相続人が遺言執行者になる場合、他の相続人との間で利害関係が生じやすく、不信感やトラブルの原因となることがあります。そのため、遺言作成時には相続人全員が納得できるよう、事前に話し合いを行ったり、公正証書遺言として残したりするなどの配慮が大切です。 |
| Q2. 遺言執行者がいる場合、相続登記は誰がする? |
| A2. 遺言執行者がいる場合、原則としてその人が単独で相続登記を申請できます。これは、2019年の民法改正により、特定財産承継遺言があるときには遺言執行者に登記申請権限が与えられたためです。 ただし、すべてのケースで単独申請が可能というわけではなく、遺贈の場合には受遺者との共同申請が必要になるなど、状況によって手続きが異なります。適切な手続きを取るためにも、専門家への相談を検討すると安心です。 ます。 |
| Q3. 遺言執行者ができないことは? |
| A3. 遺言執行者には広い権限が与えられていますが、すべての相続手続きが可能なわけではありません。たとえば、遺言に書かれていない財産の処分や、相続人同士の争いの仲裁などは、遺言執行者の権限外です。 また、相続税の申告・納付についても、相続人それぞれが自ら行うべき手続きであり、遺言執行者に代行する権限はありません。一方で、相続人の廃除やその取り消し、子の認知などは、遺言執行者にしかできない行為として遺言で指定される必要があります。権限の範囲を正しく理解し、必要に応じて司法書士や弁護士に相談することが重要です。 |
7. 相続人を遺言執行者にしてもいいが、判断は慎重に!
相続人を遺言執行者に指定することは法律上問題ありませんが、現実には注意すべき点がいくつかあります。
特に相続人同士の関係が複雑な場合や、遺産の内容に偏りがあるときは、遺言執行者の選任が相続全体の円滑さを左右します。誰を遺言執行者にするかは、信頼や能力に加えて、家族全体の状況を踏まえて慎重に判断することが大切です。
こうしたリスクや手間を避けるためには、第三者である司法書士や弁護士などの専門家に遺言執行を依頼するのもひとつの方法です。中立的な立場で公平に手続きを進めてもらえるため、相続人間のトラブルも防ぎやすくなります。
相続の専門家集団「nocos(NCPグループ)」では、司法書士や行政書士が連携し、遺言執行や相続登記などをワンストップでサポートしています。数次相続や不動産を含む複雑な相続にも対応可能です。初回相談は無料、オンラインでも受け付けていますので、まずはお気軽にご相談ください。