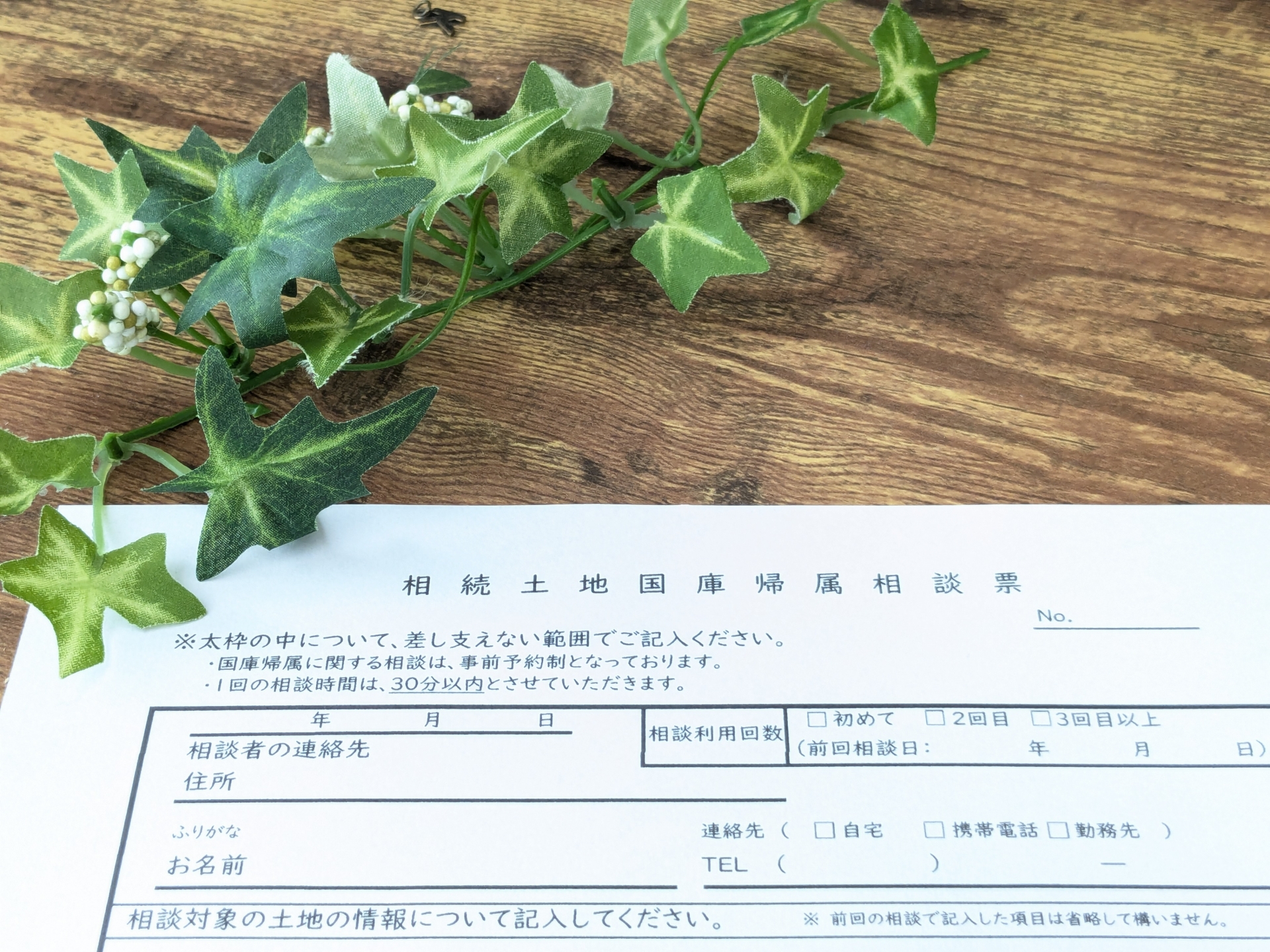この記事を要約すると
- 相続土地国庫帰属制度は、相続などで取得した不要な土地を一定の条件下で国に引き取ってもらえる制度で、山林も対象になるケースがあります。
- 土地に建物や担保権、借地権がある場合や、境界不明・土壌汚染・他人の使用がある場合は、「申請ができない土地(申請の段階で直ちに却下となる土地)」に該当するため、注意が必要です。
- 制度を利用すれば、管理や税金の負担を免れ、売却手続きも不要です。ただし申請には費用がかかり、専門家のサポートがあると安心です。
1. 相続土地国庫帰属制度とは
相続土地国庫帰属制度は、相続などで取得した不要な土地を手放し、国に引き取ってもらえる制度です。ここでは、この制度の概要や利用できる人、対象となる土地の条件について解説します。
1-1. 制度の概要と創設背景
相続土地国庫帰属制度は、一定の条件を満たすことで、相続などによって取得した土地を国に引き取ってもらえる制度です。令和5年4月27日に施行された「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」に基づいて運用されています。
この制度が創設された背景には、管理が難しい山林や利用予定のない土地が相続によって個人に引き継がれ、結果として所有者不明の土地が増加しているという社会問題があります。こうした土地は防災・環境管理の面でもリスクがあり、国としても早急な対策が求められていました。
現在では、一定の要件を満たせば土地の所有権を放棄して国に移転できる仕組みが整備されています。
1-2. 利用できる人の条件
相続土地国庫帰属制度を利用できるのは、「相続」または「相続人に対する遺贈」により土地を取得した相続人です。売買や贈与など、相続以外の原因で土地を取得した人や法人は、原則としてこの制度を利用できません。
なお、土地が共有名義の場合は、共有者全員で共同して申請する必要があります。このとき、共有者の中に相続等により持分を取得した人がいれば、他の原因(売買など)で取得した共有者も一緒に申請できます。
相続登記が未了であっても申請は可能ですが、その場合は、相続人であることを証する書類(戸籍謄本など)の提出が必要です。
制度を利用する際は以下のようなポイントを押さえておきましょう。
- 単独名義の土地:相続や遺贈(相続人に限る)で取得した人のみ申請可能
- 共有名義の土地:相続等で取得した共有者がいる場合は、他の取得原因の共有者も含め全員で申請可能
- 相続登記が未了でも申請可:この場合、相続人であることを証明する資料が必要
1-3. 帰属できない土地(申請できない土地)
相続土地国庫帰属制度では、一定の条件に該当する土地については、そもそも申請自体ができません。これは「却下事由」と呼ばれ、申請段階で法務局が確認する重要なポイントです。
以下のようなケースに該当する土地は、申請が直ちに却下されます。
① 建物の存する土地
建物が建っている土地は管理コストが高く、老朽化による取り壊しのリスクもあるため申請できません。
※ただし、建物が既に取り壊されて更地になっている場合は、建物滅失登記を済ませれば申請可能です。
※「今後取り壊す予定」の場合は、事前に法務局へ相談が必要です。
② 担保権または使用および収益を目的とする権利が設定されている土地
抵当権、賃借権、地役権、地上権などがある場合、国の管理に支障があるため申請できません。
※森林における経営委託契約や経営管理権、入会権も該当する可能性があります。
※土地の一部に電柱の地役権などがある場合も、事前に法務局へ相談が必要です。
③ 通路その他の他人による使用が予定される土地が含まれる土地
以下のような土地が一部でも含まれている場合、申請できません。
- 現に通路として使用されている土地
- 墓地内の土地(許可を受けた墓地区域)
- 宗教法人の境内地
- 用悪水路として使われている土地
- 水道用地として利用されている土地
- ため池として使われている土地
④ 土壌汚染対策法に基づき、特定有害物質によって汚染されている土地
法務省令で定める基準(施行規則第31条第1・2項)を超える汚染がある土地は申請不可です。
⑤ 境界が明らかでない土地、または所有権に争いがある土地
隣接地との境界が不明確、または他者と所有権について争いがある場合は申請できません。
※「境界が明らか」とされるには、以下の2条件を満たす必要があります
- 承認申請者が認識している境界を図面で表示できること(地物・境界標・目印など)
- 隣地所有者との認識が一致しており、争いがないこと(申請後、法務局から隣地所有者へ確認連絡が行われます)
(引用:相続土地国庫帰属制度のご案内|法務省民事局)
このような土地は、他人の権利が関与していたり、土地の状態が適切でなかったりするため、国に帰属させることができません。申請前に十分な確認が必要です。
1-4. 帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)
審査の結果、一定の条件に該当すると判断された土地は「不承認」となり、国への帰属が認められません。これは、管理や処分に著しい困難をともなうとされる土地に適用される「不承認事由」に基づきます。
以下のようなケースに該当する土地は、申請後の審査段階で不承認と判断されます。
① 崖がある土地で、管理に過分な費用・労力がかかるもの
勾配30度以上・高さ5メートル以上の崖があり、擁壁工事などが必要とされる場合は不承認となります。
② 地上の有体物によって管理・処分が阻害される土地
建物以外の廃屋・放置車両・枯れ木・竹・老朽塀などが存在し、定期的な伐採や補修が必要と判断される場合は対象外です。
③ 地下の有体物によって通常の管理が困難な土地
建材ガラ・浄化槽・井戸・古い配管・基礎コンクリなどが埋まっており、除去しなければ管理や処分ができないとされる土地は対象外です。
④ 通行権などを巡って争訟が必要となる土地
以下に該当するケースは不承認となります。
- 袋地や池・崖などに囲まれており、公道に出るための通行権が妨げられている
- 所有権に基づく使用・収益が第三者により妨害されている(不法占拠、排水の流入、立木契約など)
⑤ 災害発生や被害拡大の危険性がある土地
土砂崩れや陥没、漏出などにより人的・物的被害のおそれがあり、現状変更(埋立・工事等)が必要な土地は不承認となります。
⑥ 動物(鳥獣・病害虫等)による被害のおそれがある土地
スズメバチやクマなどが生息し、周辺の安全や農作物への被害が想定される場合も不承認です。
⑦ 森林整備が不十分な山林
間伐・造林がされておらず、森林整備計画に適合していない土地(特に人工林や標準伐期齢前の天然林)も承認されません。
⑧ 国が金銭債務を負担・承継する可能性のある土地
土地改良区などから将来的に賦課金が課される見込みのある土地。また、所有者が既に賦課金の支払い義務を負っており、国が承継することになる土地。
(引用:相続土地国庫帰属制度のご案内|法務省民事局)
なお、所有している土地が制度に該当するか確認したい場合は、法務省の「相談したい土地の状況について(チェックシート)」を活用してみてください。
2. 相続土地国庫帰属制度を使うメリット
相続土地国庫帰属制度には、相続人の負担軽減や将来的なトラブル回避など、多くの利点があります。ここでは、相続土地国庫帰属制度を使う具体的なメリットを解説します。
2-1. 農地法による制限がない
農地の売却には農業委員会の許可が必要ですが、相続土地国庫帰属制度を利用すれば、農地法による制限を受けずに、土地を手放すことが可能です。
2-2. 譲渡先探しの必要がない
通常の売却では、買い手を探す必要がありますが、相続土地国庫帰属制度では、条件を満たす土地であれば国庫に帰属されるため、不動産市場での流通性が低く、買い手が見つからないケースであっても土地を手放すことが可能となります。
2-3. 管理・費用負担の軽減と次世代への負担を回避できる
山林や原野などの土地は、固定資産税の納付や境界の維持管理、災害時の責任など、所有し続ける限り一定の負担が発生します。遠方に住んでいて現地を確認できない、利用予定がないといった場合、こうした負担は長期的に大きなストレスとなります。
相続土地国庫帰属制度を活用すれば、土地を手放すことでその後の管理義務や費用から解放され、次世代に不要な負担を残さずに済みます。特に子や孫が土地の場所すら把握していないようなケースでは、早めの対応が安心につながります。
3. 相続土地国庫帰属制度の利用にかかる費用の目安
相続土地国庫帰属制度を利用する際には、主に「審査手数料」と「負担金」の2つの費用がかかります。
まず、申請時に土地1筆あたり1万4,000円の審査手数料が必要です。これは収入印紙で納付し、却下や申請取り下げとなった場合でも返還はされません。
次に、審査を通過して帰属が承認された場合、国がその土地を管理するための費用として負担金を納付します。
負担金は、帰属が承認された土地の管理にかかる10年分の標準的費用をもとに算定されるもので、原則20万円ですが、土地の種目(宅地・農用地・森林)や区域、面積などによって金額が異なります。負担金の詳細については、法務省「相続土地国庫帰属制度の負担金 」に記載があります。
また、実際の金額は法務省の公開する「負担金計算シート(Excel)」を使って確認可能です。これらの費用は自己負担となるため、制度の利用可否だけでなく、費用対効果も踏まえて検討することが重要です。
4. 相続土地国庫帰属制度を利用する流れ
相続土地国庫帰属制度を利用するには、申請から審査、負担金の納付、そして国への所有権移転という一連の手続きを順に踏む必要があります。ここでは具体的な流れを解説します。
4-1. 承認申請
相続土地国庫帰属制度を利用するには、まず法務局に承認申請を行う必要があります。
申請者は、相続または相続人への遺贈により土地を取得した個人に限られ、法人や売買・贈与による取得者は対象外です。土地が共有地である場合には、相続や遺贈によって持分を取得した相続人を含む共有者全員で申請する必要があります。また、他の共有者については、相続以外の原因により持分を取得した場合であっても申請することができます。
申請書には、土地の位置・地目・面積などを記載し、必要書類(登記事項証明書・図面・相続関係を示す戸籍類など)を添付します。土地の状態に関する調査資料や境界に関する説明も求められるため、事前にしっかり準備しておくことが大切です。
なお、申請にあたっては、対象土地の管轄法務局「本局」へ提出する必要がある点にも注意しましょう。
4-2. 法務大臣による要件審査・承認
承認申請が提出されると、法務局が書類審査と現地調査を通じて土地の状況を確認します。
審査では、申請地が法令で定める不承認要件に該当しないか、境界や利用状況に問題がないかなどがチェックされます。必要に応じて、関係資料の追加提出や申請者への事情聴取が行われることもあります。
調査の結果、管理や処分に過度な費用や労力がかかる土地と判断された場合は不承認となりますが、条件を満たしていれば承認通知が発行されます。審査には8か月から1年ほどかかるのが一般的です。
4-3. 負担金の納入
審査を経て帰属が承認されると、申請者には負担金の納付通知が送付されます。負担金は、土地1筆ごとの管理費用として算定されます。
納付先は日本銀行やその代理店(都市銀行、ゆうちょ銀行、信用金庫など)で、負担金の通知が到達した日の翌日から起算して30日以内に納付しなければ、国庫帰属の承認が失効しますので注意しましょう。また、金額の確認には、法務省が提供している自動計算シートの利用が便利です。
4-4. 国庫帰属
負担金を期限内に納付すると、対象土地の所有権が正式に国に移転し、相続人などの元所有者はその土地に関する管理責任を完全に免れることになります。
所有権の移転登記は国が自動的に行うため、申請者側での追加手続きは不要です。
その後の管理や処分はすべて国が行い、申請者には一切関与の義務がなくなります。特に山林などの管理が難しい土地においては、この制度を活用することで長期的な負担やトラブルから解放される大きなメリットがあります。
5. よくある質問・Q&A
相続土地国庫帰属制度については、申請条件や手続きの詳細に関して多くの疑問の声があります。ここでは、特に質問の多い項目をQ&A形式でわかりやすく解説します。
| Q1. 登記していない山林でも申請できる? |
| A1. 相続登記されていない土地でも申請は可能です。 ただし、その場合でも申請者が相続によってその土地を取得したことを証明する必要があります。たとえば、被相続人名義のままになっている土地であれば、相続関係を示す戸籍類や固定資産評価証明書などを用意し、法務局にて所有権の取得を説明できる状態にしておく必要があります。 |
| Q2. 境界が一部不明な土地はどうなる? |
| A2. 境界が一部不明な土地でも、状況によっては申請が認められることがあります。 確定測量までは不要ですが、少なくとも「境界明示」がなされていることが必要です。具体的には、隣接地所有者との間で境界について合意があり、境界標が設置されているなど、客観的に範囲が確認できる状態が求められます。反対に、境界争いがある、または境界線が完全に不明で調査が難航する土地は、審査の段階で不承認となる可能性が高くなります。 |
| Q3. 複数人で共有している土地は申請できる? |
| A3. 共有名義の土地でも相続土地国庫帰属制度を利用することは可能です。 ただし、共有者全員が制度の利用に同意していることが絶対条件となります。たとえば、兄弟姉妹で共有している山林を申請する場合、1人でも反対する共有者がいれば手続きを進めることはできません。そのため、制度を利用する前に、他の共有者としっかりと協議し、同意書を取り付けておくことが重要です。合意形成が難しい場合は、弁護士など専門家を交えて話し合うことが大切です。 |
| Q4. 土地の一部だけを申請することはできる? |
| A4. 土地の一部だけを相続土地国庫帰属制度に申請することは、原則としてできません。 制度の対象は「一筆の土地単位」であるため、地番単位で分筆されていない限り、その一部だけを手放すことは認められていません。たとえば、山林の一部のみを国に引き取ってもらいたい場合は、まず分筆登記を行って対象部分を独立した一筆とする必要があります。そのうえで、帰属申請を行う形になります。分筆には測量や登記手続きが必要となるため、事前に専門家と相談することをおすすめします。 |
6. 相続した山林に困ったら、専門家に相談を
相続した山林について、「使い道がない」「管理が大変」と感じる方は少なくありません。山林は、税金や管理の負担が続く限り放置するわけにもいかず、悩みの種になりがちです。
相続土地国庫帰属制度は、不要な土地を国に引き取ってもらえる制度として注目されていますが、申請には境界の確認や申請書類の準備、法務局とのやり取りなど、専門的な知識と手続きが必要になります。
とくに山林の場合は、「境界が不明」「第三者が利用している」「急傾斜地で危険」といった事情があると、申請が難しくなるケースもあります。また、制度の対象かどうかの判断や、負担金額の見積もり、分筆や測量の必要性など、個別に検討すべき点も多くあります。
こうした複雑なケースでは、司法書士や土地家屋調査士などの専門家に早めに相談することで、申請の可否や進め方が明確になり、時間や労力のロスを防ぐことができます。相続にまつわる不動産の悩みは、放置せずに早めの対応が肝心です。
相続手続きの専門集団「nocos(NCPグループ)」では、司法書士や行政書士など各分野のプロが連携し、相続土地国庫帰属制度をはじめとした複雑な土地相続にも対応しています。初回相談は無料、オンライン対応も可能です。山林相続にお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。